Knowledge基礎知識
特別受益の請求方法は?
「お兄さんは家を建ててもらったのに、私たちには何もしてくれなかった。それなのに遺産は平等に分けるの?」 このような疑問を持ったことはありませんか?親が亡くなったとき、兄弟の中で一人だけが生前に大きな援助を受けていたり、お金をもらっていたら、他の相続人は不公平に感じるかもしれません。
こうした状況を公平に調整するために法律で定められているのが「特別受益」という考え方です。
今回は、特別受益とはどういうものか、そして特別受益を考慮して遺産を分けたい場合にどうすればよいかを確認します。
特別受益とは
特別受益とは、簡単に言うと「生前にもらった分は、相続で差し引きますよ」という仕組みです。
特別受益とは、相続人のうちの一部のひとが被相続人から生前に財産の贈与を受けていた場合に、それを「すでに相続の一部をもらっていた」として扱います。
具体的には、以下のような贈与が該当する可能性があります。
- 住宅の購入費用や建築資金の援助
- 結婚や進学のための多額の費用
- 事業資金の提供
- 土地や建物を贈与してもらった場合
こうした贈与は「生前贈与」と呼ばれることもありますが、そのなかでも特に相続人に対して贈与されたものを特別受益と呼びます。
なぜ特別受益が問題になるのか
特別受益は、相続人の間の公平を保つために重要です。
たとえば、兄が住宅資金として1000万円をもらっていた場合、弟や妹と同じ割合で遺産を分けるのは公平性に反します。
そのため、特別受益に該当する場合は、「持ち戻し計算」という方法で、各相続人が受け取る遺産の額(相続分)が調整されます。
持ち戻し計算の簡単な例
田中家の場合:お父さんが亡くなり、残された財産は2000万円
相続人は、長男と次男の2人
– 長男:生前に住宅資金として800万円の援助を受けていた
– 次男:特に援助は受けていない
計算方法
1. まず、生前の援助も含めて全体の財産を計算
2000万円(残った財産)+ 800万円(長男への援助)= 2800万円
2. これを2人で等分(法定相続分での分割)
2800万円 ÷ 2 = 1400万円ずつ
3. 実際に受け取る金額
- 長男:1400万円 – 800万円(既にもらった分)= 600万円
- 次男:1400万円
このように計算することで、結果的に兄弟が平等になります。
特別受益の請求方法とは
特別受益があると思われる場合、その調整を求めるには、遺産分割協議などで特別受益を主張する必要があります。
遺産分割協議
特別受益の問題は、まず相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で解決を試みます。
話し合いの場では、特別受益を受けたと考えられる人に対し、「被相続人からこのような贈与があった」「金額は○○万円程度」など具体的な事実を示すことが重要です。
たとえば、「お兄さんは家を建てるとき、お父さんから800万円援助してもらいましたよね。それを考慮して遺産を分けませんか?」などです。
贈与の内容や金額がわかる証拠があると、話し合いがスムーズに進む可能性が高くなります。
話し合いを成功させるコツ
- 感情的にならず、事実だけを冷静に伝える
- 金額や時期を具体的に示す
- 証拠となる書類があれば準備しておく
遺産分割調停の申立て
相続人同士の話合い(遺産分割協議)で解決(合意)できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てを行います。
調停では、裁判官や調停委員という第三者が間に入って話し合いを進めてくれます。
法的な知識を持った専門家が関わるため、より客観的な判断が期待できます。
調停でも解決(合意)できない場合は、「遺産分割審判」という手続きにそのまま移行し、最終的には、裁判所が判断(審判)を下します。
証拠を集める
特別受益を主張するためには、証拠が重要となります。
集めておきたい証拠
- 銀行の振込記録(通帳のコピーなど)
- 贈与の際の契約書
- 不動産の登記簿(土地や建物をもらった場合)
- 親の日記や手紙
- 第三者の証言(親戚や知人など)
請求の際に注意すべきポイント
贈与された財産であっても、それが「特別受益」として認められるかどうかは状況によって異なります。
たとえば、親が子に対して生活費を援助していた場合、それが通常の扶養義務の範囲と判断されれば特別受益とは認められない可能性があります。
まとめ
特別受益は、公平性を保つための制度として重要です。
特別受益の問題は、多くの家族が直面する可能性のある身近な問題です。
しかし、実際の請求には、証拠の準備や手続きの理解が必要となるため、想像しているよりも手間がかかる可能性があります。
不安な場合や話し合いが難航する場合には、弁護士に相談することも検討してみてください。
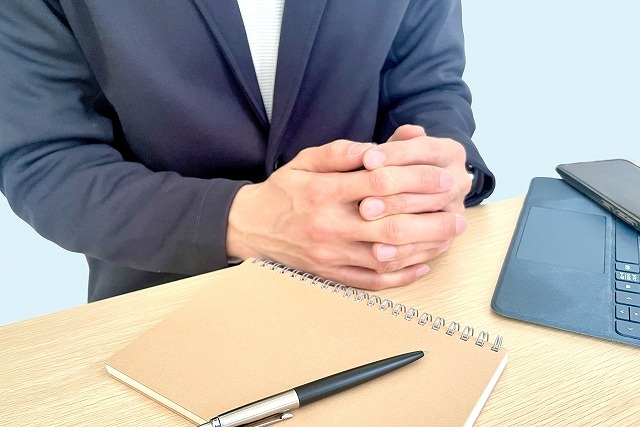
著者について
弁護士 川村 勝之
